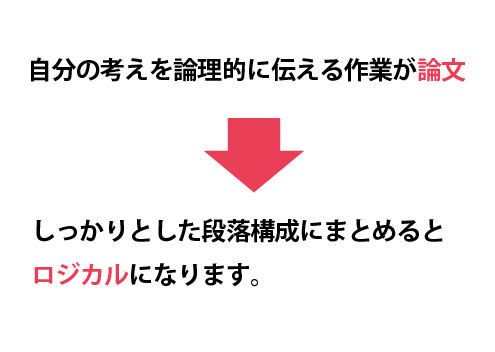
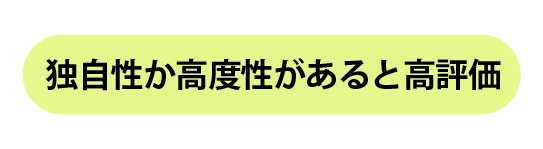
修士論文とはどんなものか、そして入試で課される筆記テストの論文(小論文、専門科目など)で何がチェックされるのかについて考えてみましょう。まず、筆記試験でよく出題されて来た格差社会についての答案例を見てみましょう。
「格差社会について論じなさい。」
ダメな答案
格差社会という言葉が毎日のように新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどで報道されている。格差社会とはヒルズ族に代表されるような富裕層と、ワーキングプアーとして低賃金で働いている人たちの間で、ものすごい格差のある社会のことを言う。
アメリカ合衆国では、一部のエリートの勝ち組と、そうではない人たちの間にものすごい格差のある社会である。リンカーンは丸太小屋に生まれたが努力をして、大統領まで登りつめた。アメリカにはそうした大出世の事例が多くあり、そのような出世物語は、アメリカンドリームと呼ばれている。移民してきたアーノルド・シュワルツェネッガーが、カリフォルニア州知事になったこともアメリカンドリームと言えるだろう。
現在の日本の格差社会は、アメリカのような出世はしにくい過酷な格差社会である。一度、負け組になってしまうと、非正規雇用の仕事になかなか就くことができなくなり、ネットカフェ難民や、ホームレスから抜け出すことが難しい。ニートやフリーターであった経歴は企業にとって嫌がられるために、そうした人たちはワーキングプアーとして働いていかざるを得ない。
日本の格差社会はよくない格差社会である。アメリカのように、誰でもが偉くなってお金持ちになれる社会に政治家にはしてもらいたいものである。
(コメント)
このような答案は、政治家にはちゃんとしてもらいたいということしか言っておらず、街頭インタビューで誰でも言えそうなことしか書いてありませんので、いい点をもらえません。
「格差社会について論じなさい。」
まぁまぁの答案
格差社会という単語は、現代日本の性格を現すキーワードと言える。戦後日本は比較的格差のない社会だったが、90年代からの新自由主政策の影響により、非正規雇用の常態化、リストラの横行などにより、日本は格差社会になったという指摘が多くなされている。本論文では、教育の視点から、格差社会のメカニズムを論じたい。
確かに、誰もが学校の勉強を頑張って能力を磨けば、格差社会の負け組にはならなくて済むという見方もできる。しかし、私はゆとり教育が格差を助長したのではないかと考える。
ゆとり教育は、それまでの詰め込み教育を反省し、個性を伸ばすことを主眼として始まった教育のあり方である。一見するとゆとり教育は、学校の勉強が全てではないという価値観を社会に広め、多様な個性的な人材を養成するようにも思われる。しかし実際のところは、教育熱心で経済的なゆとりのある家の子が人生の選択肢を増やし、教育に熱心ではない家庭の子が人生の選択肢を減らすことにつながり、格差の固定化に結びついている。教育熱心で、経済的な余裕のある家の場合、学校のカリキュラムがやさしくなると親が子どもの将来を心配して、塾や習い事に通わせるようになり、学力が向上する。その一方、経済的余裕がなかったり、教育への関心が薄い家の子どもは、子どもを塾に行かせるという発想がないため、ゆとり教育になるとただ単に遊んで過ごす時間が増えるだけとなり、学力が身につかない。そして進学において大きな差が出て、のちのちの職業選択の幅に差が出るのである。
以上述べて来たように、ゆとり教育によって、格差社会が助長されている側面が少なくないと私は考える。
(コメント)
この答案は、格差社会が生まれるメカニズムを分析できている点はいいですね。しかし、この書き方だと、賢い中学生、高校生で書けるような答案です。
「格差社会について論じなさい。」
ポイントが高い答案
格差社会という単語は、現代日本の性格を現すキーワードと言える。戦後日本は比較的格差のない社会だったが、90年代からの新自由主政策の影響により、非正規雇用の常態化、リストラの横行などにより、日本は格差社会になったという指摘が多くなされている。本論文では、教育の視点から、格差社会のメカニズムを論じたい。
確かに、誰もが学校の勉強を頑張って能力を磨けば、格差社会の負け組にはならなくて済むという見方もできる。しかし、私はゆとり教育が格差を助長したのではないかと考える。
フランスの社会学者ピエール・ブルデューは、著書『ディスタンクシオン』の中で、ハビトゥスという概念を論じている。ハビトゥスとは、その階級における特有の習慣、行動様式のことである。例えば、上級ホワイトカラーの子弟は親と同じく高学歴になり、親と同じく社会的ステータスが高い仕事に就くことが多く、ブルーカラーの子弟は高い教育を受けず、親と同じくブルーカラーになってゆくことが多い。ブルデューは、この現象を、経済資本と文化資本に着目して解明した。上流の家庭では、両親の学問や教養への関心が強く、そうした親の行動様式や習慣、趣向から、子どもに高い教育費をかけ、結果的に試験を通過し、高い地位へと登ってゆくのである。一方のブルーカラーの家の子は、親が子どもに高い教育を受けさせよう発想がなく、読書の習慣があまりないため、子どもも教養がなかなか身につきにくく、難関試験を受けもせず、通過もせず、親と同じくブルーカラーの職に就き、低い賃金に甘んじるのである。つまりホワイトカラーもブルーカラーも親の文化に似るということであり、これを文化の再生産とブルデューは名づけた。現代日本の状況を考えてみると、ゆとり教育によって文化資本、経済資本が高い家庭の子は、塾や習い事に通い、メリトクラシー社会に適合的なハビトゥスを身につけるが、そうでない家の子は、そうしたハビトゥスを身につけにくくなっている。つまり、生まれた階層という属性によって、格差が固定化されやすい社会になっているのである。
以上述べて来たように、ゆとり教育によって、格差社会が助長されている側面が少なくないと私は考える。
(コメント)
この答案は、格差社会になるメカニズムを、大学レベルの学術理論を用いて分析して書けていますので、これから大学院に入って研究しようとしている人としてだいじょうぶそうだと思われていい点をもらいやすい答案です。大学レベルの知識を持っていることを採点官にアピールすることは大切です。
テレビ番組のコメンテーターに例えてみると、、、、
テレビ番組のコメンテーターには、主婦代表のような人、ギャル、お笑い芸人、経営者、大学教授などがいます。ギャルタレントは、身の回りのことをしゃべり、主婦代表のような人は、台所からの感覚を話したりし、お笑いタレントは、笑いをまじえて一般人の視点からのコメントをしますし、若者代表のような人は、若者が将来に希望を持てるような社会づくりを訴えたり、周囲の若者の声を紹介しながらコメントをします。
そして、大学教授は、その人の学問的バックグラウンドから、一般人にも分かりやすいコメントをします。例えば、故・森永卓郎さん(経済アナリストで獨協大学経済学部教授)はしばしば、小泉竹中構造改革による新自由主義の経済政策が日本を格差社会にした、など批判をしていたように、少し学問的なキーワードを盛り込んだコメントをしていました。
また、ハーバード大学出身のパックンマックンのパックンは。ハーバード出身者ならではのデータや学術理論を盛り込んだコメントをしていますよね。その一方で、放送専門学校出身のデーブ・スペクターさんは、ペラペラの日本語でダジャレを盛り込んだコメントをしています。長くコメンテーターのオファーがある人にはそれぞれの持ち味があります。
林修さんと、ホストのROLANDさんがテレビで対話をしていましたが、ROLANDさんが林修さんに、「なんで勉強ってしなくちゃいけないんすか?」と質問したところ、林修さんは、「そういう質問をする人は勉強しなくてもいいんですよ。」と答えていました。これは学校の勉強が必要な世界で生きていく人と、そういう知識がいらない人がいるので、みんなが学校の勉強をしなくてもいいんじゃないか、という話だったと思います。
大学院を受ける人は、大学教授と学問的な会話をしていこうと思っているから受験をするわけですから、何らかの学問的な言葉、理論を使った会話ができる人だと思っていただけるといいですよね。
ですから、高学歴なパックンや大学教授のコメンテーターのような言葉遣いを答案に書けるといいですよね。パックンや教授と同じような言語共同体の人なんだなと思ってもらえるように心がけたいですね。
コミュニティによって暗黙の了解ってありますよね。学問理論をまじえて話をすることは各学問分野ごとに行われています。それなのに、日常生活の言葉だけでしゃべる人がいると、ええっ?となってしまいます。
旧ジャニーズに例えると、キムタク的なヤンキーっぽい言動ではなく、ニュースキャスター経験がある櫻井翔くん(嵐)、小山慶一郎くん(NEWS)、また大学院を出ている阿部亮平くん(SnowMan)のような言葉づかいの雰囲気の答案がいいですよね。
女性タレントだったら、慶應卒のトラウデン直美さん、これまた慶應卒の山崎怜奈(元乃木坂46)さんのように、大学で学びさらにコメンテーターとして成長しようと学び続けているような人のような言葉づかいの答案がいいですよね。
元AKB48で元HKT48の指原莉乃さん、子役出身の芦田愛菜さんはいずれも賢い人だと思いますが、大学院を受ける人は、学校文化とは親和性があまりない指原さん的な言動よりも、学校文化になじんでいる芦田愛菜さんっぽい言葉づかいの答案を書けるようになると理想的ですね。
つまり、大学レベルのキーワード(勉強している人じゃないと言ったり書けない学問の言葉。これが高度性)を盛り込んで、しっかりとした段落構成で答案をまとめるといい点をもらいやすいです。
論文の書き方を事前にしっかりと学んでおくべき理由
大学院の修士課程では、修士論文を2年間(近年は、1年間で修士号と取得できる大学院や、1.5年で修士号と取得できる大学院などもある。)かけて作成することが最終目的である。
修士論文(修士論文を書かなくても卒業できるところもある。リサーチペーパーといって、実務での課題にいかに取り組みどう改善したかをまとめればすむような論文を出せば済む大学院もある。)では、自分で問いを設定し、その問いを当該学問分野の理論を用いて明らかにする。
入試においては、ちゃんと修士論文を書けるかどうかをチェックされる。大学院入試の小論文は、八百字から千字ほどのケースが多い。修士論文は、4万字以上のことが多い。入試の小論文は、修士論文のいわばミニチュア版である。
「よくある修士論文の流れ」(2万から4万字程度)
序 本論文の問題設定
1 先行研究の批判的検討
2 仮説の提示
3 ~~~~~の現状
4 ~~~~~の考察
結 ~~~~~の結論
「よくある小論文、論文の流れ(修士論文のミニチュア版)」(800字から1200字程度)
1 問題設定
2 意見提示
3 展開(本論)
4 結論
明らかにしたい問題を限定した上で、論理的に読み手に自説を展開するのが修士論文をはじめとする学術論文である。それを書ける人かどうかをチェックされるのが入試の論文である。1000字程度のものをまともに書けない人が、2万から4万字の論文を書けるはずもないのは当然であるため、事前学習をやっておきたい。
入学させた後で、修士論文を作成することに非常に困難をおぼえる人だと発覚してからでは、大学院生本人もつらい思いをするばかりではく、教授サイドとしても指導困難となり、たいへんな労力がかかり、心労もたまってしまい、お互いが不幸なことになる。そうした不幸を回避するためのチェックとして、論文試験があるのである。
大学院入学前に論文の勉強をしておくことは、もしも入試が面接だけのところを受験する人にとっても重要である。特に社会人で、学校の勉強が久しぶりの方は、入学後の授業での発表の際のレジュメ作り、授業のレポート作り、修士論文作りがスムーズに進むからである。大学院で求められる文章がどういうものかを把握しないまま入学しては、入った後に、空気を読めない院生となってしまっては、みそっかすになってしまい、大学院内で居場所がなくなってしまうということになりかねない。
入学後になってから論文の書き方を勉強するようでは、入ってから単位を取得することが難儀になるとともに、修士論文の作成のスタートダッシュができず、ぎりぎりで修士論文を何とか形にしてお情けで修士号をもらうということになってしまいやすい。博士課程に進学したくなったとしても、受け入れてもらえないという事態を招いてしまう。
であるからして、受験にあたって論文、小論文とは何かということをしっかりと学んでおいていただきたい。
小論文・論文へのよくある誤解
小論文への誤解1
自分の主張を明確にすれば良い。
→小論文、論文は、自分が言いたいことをやみくもに言うのではなく、論理的に筋道立てて説明しなくてはならない。
受験生がどのような思想信条を持っていてもそれは自由である。しかし、意見が異なる相手に対して、ただ単に自分の主張を延々と感情を露わにして繰り返したとしたら、相手は困り、今後関わりたくないと思うようになってしまうのはごく自然なことである。
特定の誰かや思想や団体が悪いと主張するとしても、ただ単に嫌いだ、気持ち悪い、良くない、ひどい人だ、悪だくみをしているに違いない、と何の根拠もなく印象を述べ続けたとしたら、その人は知的な人とは思われることはない。特定の人や思想や団体を批判するならば、その人物や思想や団体のどういう点がどういう理由で好ましくないのかを指摘した上で批判せずに、自分の感情をぶつけるだけでは単なる駄々っ子と同じであり、大学院で学ぶ知的水準にはとてもないと入試でばれて不合格になってしまうのである。
例えば、「格差社会について論じなさい。」という出題に対して、
悪い例
① 格差社会は望ましいかどうか論じたい。
② 格差社会の現状を説明。
③ 格差社会は悲惨だ。負け組はかわいそうだ。一部の金持ちはずるい。ひどい人たちだ。だから格差社会はよくない。
④ 以上述べて来たように、格差社会はよくない。
などという流れで答案を書いて提出してしまえば、定員を埋めることに必死な大学院でもない限り合格は難しい(定員を埋める気がない大学院の方が多いという現実があります)。これではワイドショーの街角インタビューで答えるいわゆる庶民と同じレベル(テレビ的におもしろくするためにいかにもな人を登場させているのであろう)であり、勉強をしていなくても誰でも言えることである。単に自分の印象、感情を吐露しているだけであり、論理的な思考能力をまったくアピールできていない。もしもこのような答案でよければ、思いやりがあるならば合格ということになってしまう。大学院入試は、思いやり選手権ではない。論理的思考能力を競争する場である。
大学院に入りたい人は、ワイドショーでいえば、コメンテーターをつとめる教授のようなコメントを少しはできるというところを見せなくてはならないのである。
望ましい例
① 格差社会は望ましいかどうか論じたい。
② 確かに、勝ち組、負け組に分かれたのは個人の努力の差という考え方もなりたつ。
しかし、今日の格差は、新自由主義の経済政策の結果生じたものであり、個人の努力ではいかんともしがたい側面が強いのではないか。
③ (新自由主義の経済政策による格差拡大のメカニズムの説明。)個人の努力ではどうしようもない社会変動という大きな変化によって格差が生まれた。これは不条理である。
④ 以上述べて来たように、私は格差社会は望ましくないと考える。
このように、新自由主義の経済政策という勉強していなくては絶対に書けないことを盛り込みつつ、筋道立てて自説を展開すれば、採点官と意見が異なっていたとしても、採点官はその受験生が勉強していることは把握でき、なおかつ論理的思考能力がある受験生であることが理解でき、意見は異なっていたとしても高いポイントをつけてくれ、合格の可能が高いだろう。
大学院でのゼミナールでは議論を行うのであるが、その場にただ単に自分の感想を延々と言い続ける人がいては、議論の邪魔になってしまうため、そうした人を排除し、教育水準を保つために、論理的思考能力がない人は合格させないのである。
小論文への誤解2
勉強した事実を羅列して知識をアピールすると良い。
→暗記した事実を並べるだけでは何も考えていないことをアピールしてしまう。分析を入れないと高ポイント獲得は無理である。暗記をがんばる思考停止の人は大学院では喜ばれない。
研究計画書の章でも書いたとおり、ただ単に事実を羅列する人がしばしばいるが、それではその受験生は暗記は得意だということはわかるが、何も考えていないと自分でアピールしてしまっていることになり、高いポイントをもらうことは難しい。
インターネットで検索すればすぐにある程度の情報が集まる時代となった今日は、それらの情報を組み合わせて思考することが重要であり、その思考のプロセスを答案に反映させてアピールし、ポイントを稼ぐことが合格の秘訣である。
小論文への誤解3
連絡事項を書くビジネス書類が書ければ小論文が書ける。
→ビジネス文書とは違う学術的な言語共同体である大学院に入るため、大学院で求められる文体を覚える必要がある。
会社での書類と学術論文の言葉は異なる。会社の書類で大学教授のような文章を書く人がいたとしたら、その人は空気を読めない邪魔な人になってしまうだろう。逆に大学において会社の書類のようなものしか書けない人がいては、教授にとってはその院生は空気の読めない邪魔な人になってしまうだろう。
専修大学を卒業していたそのまんま東さん(東国原英夫)は、『ビートたけし殺人事件』など小説を出版するなど文才があることで知られていたが、早稲田大学への社会人入試の準備のために小論文を始めた際に、いったい何をどうかいたらよいのかさっぱりわからなくなり、苦労したことが自伝『芸人学生』に記されている。
場所によって求められているものが違うということは把握して受験に望みたい。大学院で求められる文章はどういうものなのかを知るためには、大学入試の現代文や小論文の参考書を読むことを強くおすすめしたい。大学入試の現代文や小論文の課題文として出題されているのは、学者や評論家の文章である。大学院で求められる文章がどのようなものかをつかむためには、大学受験の現代文と小論文の参考書はうってつけである。
これから大学院に進学するみなさんが書いた修士論文、そしてその後、学会に入って書いてゆく論文が何年か後、十年後に、十数年後に、大学受験の現代文や小論文の課題文になる可能性もあるわけである。大学入試で出題されてもおかしくなさそうな文章に近づくことを意識して準備するとよいだろう。しかしだからといって、自分らしさを失ってはしょうがないことであるため、自分らしい文章に大学教授が使うような言葉、言い回しを肉付けしてゆけばよいため、あまり構える必要はないということをお伝えしておきたい。
小論文への誤解4
難解な文体にすると良い。
→本人も何が言いたいのかわからないような文章にしたり、単純なことをやたら難しくする必要はない。
これの研究計画書の中で述べた通りであるが、難解で抽象的な文章にすればよいということでは全くない。明治擬古文にする必要はまったくないのは当然であるが、小林秀雄のような文章にする必要もまったくない。
自分のもともとの文章にプラスして、大学受験で出るよな評論文のキーワードや、大学レベルの様々な学問分野の知見を盛り込みつつ、自分なりの大学院用の文章が書けるようになってゆけばまったく問題ないので、そこまで心配することはない。今の自分の実力に少しプラスして、もう少し堅い文章を書けるようにすれば十分である。
難しいことを引用し過ぎるのも問題である。「ソーカル事件」という思想界で大騒ぎになった事件がある。この事件は、物理学者のソーカル氏が、文化系の思想家たちが自然科学の知識を都合よく使って論文を書いているが、自然科学の知識の使い方がおかしいことに疑問を感じたことに端を発する。ソーカルは、思想家に一石を投じるために、自然科学の知識をあえてめちゃくちゃに使って権威づけをしたうその思想の論文を、文系の雑誌に投稿し、審査が通ったら思想界の自然科学の知識の使い方がおかしいという証明になるということで、フランスで最も権威のある思想雑誌に、いんちき論文を投稿した。その結果、なんど見事に審査に通り雑誌に掲載されたため、ソーカルはほんとうのことを公表したところ、大騒ぎになたという事件があった。
難解な自然科学の知識を織り交ぜて論じれば、読み手を幻惑させてだませることはあるかもしれないが、大学院受験生が自分でもよくわかっていない知識を織り交ぜて難解な文章にしたところで、教授陣には見透かされることにまずなると思われるため、自分がちゃんと勉強し、わかっていることを引用して論文を書くことをおすすめする。
小論文への誤解5
名エッセイスト、文豪のような味わいがある文章が良い。
→論理的思考能力をアピールするのが大学院入試の論文では求められている。
大学院受験における論文、小論文は、芸術作品ではないため、芥川龍之介や谷崎潤一郎や川端康成のような小説家のようになる必要まったくない。また、辛酸なめ子や斎藤美奈子や小倉千加子のようなおもしく本質を突くエッセイイストのようになることを目指す必要もまったくない。
名人芸を入試の時点では目指す必要はまったくない。論理的に理詰めで読み手に伝えることができれば十分である。てにをは、がおかしいのは論外であるが、段落構成がしっかりとしており、自分が設定した論点を筋道立ててしっかりと結論にまで持って行っていれば、ポイントをそう引かれることはない。
味わいのある論文を書ける教授もめったにいないわけであるため、受験生が味わいのある論文を書けなければいけないということはまったくない。
小論文への誤解6
入試本番で問題を見てから書くことを考えればよい。
→事前に使えるネタをストックしておき、本番で問題を見て、ネタの引出しの中から使えるものを組み合わせて応用して書くとよい。
これもよくある誤解である。入試本番の出題を見てから、何を書くのかを決めればよいと思っている人がいるが、それではいいことを思いつかないことが多く、時間が足りなくなることも多い。マラソンを走る予定の人が、練習をすると疲れるので本番まで練習せずにずっと休んでおいては絶対によく走れないことと同じである。事前に勉強せずに小論文の本番に臨んだとしても、いいことを思いつく可能性は極めて低い。
テレビのワイドショーのコメンテーターの教授のことを考えていただきたい。次から次に出てくる話題に対して、コメンテーターの教授は自分の専門知識の引出しの中から何らかのネタを引っ張って来てコメントをしている。その場その場で考えてコメントをしようと思っても、とっさにいいことを言えるはずもない。自分の知識のストックの中から、コメントをできる人でなければテレビのコメンテーターはつとまらないのである。
入試の小論文、論文でもこれは同じことで、事前にネタをストックし、それらをうまく使って、うまく組み合わせて論文を構成して記述することが合格のコツである。
具体的な筆記試験の勉強方法、書き方
専門科目とは、一般的な知識で書けるような問題ではなく、当該の学問分野の知識を問われる試験である。例えば、「格差社会について論じなさい。」というのが小論文であるとすれば、「ケインズとフリードマンの経済学理論を比較しつつ今日の格差社会を論述せよ。」が専門論文である。専門科目対策としては、その分野の入門書を数冊読み、全体像をつかむことがまず重要である。
社会科学とは、社会の見えない構造を明らかにする学問分野であり、人文科学とは文化のなかの見えない構造を明らかにする学問であり、自然科学は自然法則の見えない構造を明らかにする学問である。道徳的なことを書くことは、大学院入試では求めらていない。小学校、中学校、高校の教師は、道徳的な作文を学生に求め、道徳的ないい子を教師は好むが、大学の教員はまったく発想が異なる。大学教員が好む学生は、他人とは違ったものの見方をできる人物である。
専門論文と小論文には、事前に知っておくべき専門知識の量と幅の違いはあるが、基本的には書き方は同じである。論文を上達させる早道は、問題設定をしっかりし、自説を展開する際に大学レベルの学問的知識を織り交ぜることである。学問的知識を盛り込んで記述すれば、その理論を記述するだけでも字数が稼げ、採点官の教授は、学問的理論を使えている受験生に対しては好印象を持つというメリットがある。教授としては、いちいち簡単なことを説明せずに、対等に学問の話をできる学生に来て欲しいと思っているため、学問的な理論が好きで、本を読んでいるし、今後もどんどん知識を吸収したいとアピールするような論文(小論文)の答案を書くのが必勝法だ。
論文を上達させる3つのやるべきこと
1 段落構成のマスター
2 ネタのストック
3 応用力養成
1 段落構成
段落構成さえある程度しっかりしていれば、そこまで悲惨な答案はなかなかできあがらない。
段落構成の基本型A
1、 問題設定(論点1つ)
2、 意見提示
3、 本論
4、 結論
段落構成の基本型B
1、 問題設定(論点1つ)
2、 本論
3、 結論
段落構成の基本型C
1、 問題設定(原因と解決など論点が2つ)
2、 原因
3、 解決策
4、 結論
段落構成の基本型D
1、 問題設定(~の理由を以下に述べる)
2、 1つめの理由
3、2つめの理由
4、~つめの理由
~、結論
これらの段落構成を基本に自分なりにアレンジするといいだろう。
段落構成の基本型Aの場合。
1、問題設定(論点1つ)2、意見提示、3、本論、4、結論
1問題設定では、~~について論じたい。と限定された問いを設定する。
2意見提示では、確かに~~~である。しかし私は~~~と考える、と記す。
3本論では、2の流れをふまえ、自説を展開する。
4では1から3までの話を総括したまとめを書く。
第一段落で何を論じるのかをテーマを明確にした上で書き始める。二段落では確かに~のように自分とは異なる意見への目配せをして柔軟性、視野の広さをアピールしつつ字数も稼ぎ、しかし~のところへ自分の意見を持ってくるのである。第三段落では、自分の関心、専門分野の中から勉強して来た学問的知識(勉強していないと書けないような知識を使って勉強していることをアピールしてポイントゲット)第四段落では、第一段落で設置した問いに対する結論をそれまでの流れを総括するようにまとめるのである。
第一段落で立てた問いに対する答えを最後にしっかりとまとめれば、最初と最後のつじつまが合うため、段落構成がしっかりしていたら、そこまで悲惨な答案にはならないため、まずは段落構成をしっかりとマスターしたい。
段落構成の基本型B
1、 問題設定(論点1つ)
2、 本論(長い場合は段落を分割)
3、 結論
基本形Bの場合は、基本形Aとは違い、確かに~、しかし~の部分をカットした形式である。時間の都合、時数の都合によっては、確かに~、しかし~の部分はカットしてもよいだろう。
1で問題設定をし、2で理論を書き、次の段落で理論を使って考察し、ラストの段落でまとめるといいだろう。
段落構成の基本型C
1、 問題設定(原因と解決など論点が2つ)
2、 原因
3、解決策
4、結論
基本形Cの場合は、論点が2つの場合である。例えば、格差社会は良いか悪いかを論じる場合は、基本形Aや基本形Bの段落構成を使うといいだろうが、格差社会の原因と是正策を論じる場合は、基本形Cが便利である。
1で格差社会の原因と対策を論じたい、と論点を設定する。2では格差社会の原因を新自由主義や小さな政府などのネタを盛り込んで論実する。3では是正策をNPOなどのネタを使って記述する。4では格差社会の原因と是正策をコンパクトに繰り返し述べてまとめる。
字数の都合によっては、1と2の間に、確かに~、しかし~の段落を作って字数稼ぎと視野の広さをアピールしてもよい。
段落構成の基本型D
1、 問題設定(~の理由を以下に述べる)
2、 1つめの理由
3、2つめの理由
4、~つめの理由
~、結論
基本形Dは、裏ワザである。論文の構成がどうしても思いつかない時や、こまごまとしたアイデアは思いつくが、これ!というアイデアがない時や、時間がない時に使える。
1でまず結論を言い切ってしまい、その理由を以下に次々に述べていくのである。字数が埋まるまでと、時間がある限り段落を作り、字数と時間がそろそろ終わりになれば、ラストにまとめの段落を作るのである。
例えば、
1、 格差社会と言われているが私は格差は是正するべきだと考える。以下にその理由を述べたい。
2、 1つめの理由
3、 2つめの理由
4、 3つめの理由 ~~~
X、まとめ
以上、基本型AからDを順を追って見て来た。各自、とっつきやすい型があると思われるが、まずはこの4つの型をマスターし、自分の得意な流れを作ってゆくと省エネで勉強が進み、合格が近づくだろう。
赤田総研では、おひとりおひとりの状況、ニーズに合わせた筆記試験対策をしていますのでお気軽にご相談ください。
2 ネタのストック
ネタのストックとは、いろいろな学問分野に出て来る理論を自分の頭に入れることである。
例えば、明治大学大学院において「ブランドについて論じなさい」という出題がありましたが、経済学者のウェブレンは、顕示的消費という理論を提唱したが、これは~~~~~~という理論であり、~~~~~~~と書いていけるような理論を頭にため込んでいくということである。テレビのコメンテーターをしている教授は、出て来た話題に合わせて、○○学では~~~~~~とコメントしますが、そのような知識の引き出しを増やすことが、ネタのストックです。
3 応用力養成
応用力とは、頭の中にストックしたネタをいろいろな出題に応じて、どれを使ってしっかりとした段落構成にして書き上げるかの練習です。
赤田総研では、おひとりおひとりの状況、ニーズに合わせた筆記試験対策をしていますのでお気軽にご相談ください。筆記試験があったら無理な人の場合、筆記試験がなくて済む大学院を紹介します。